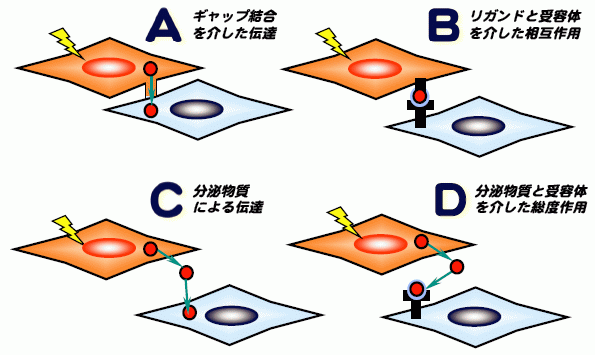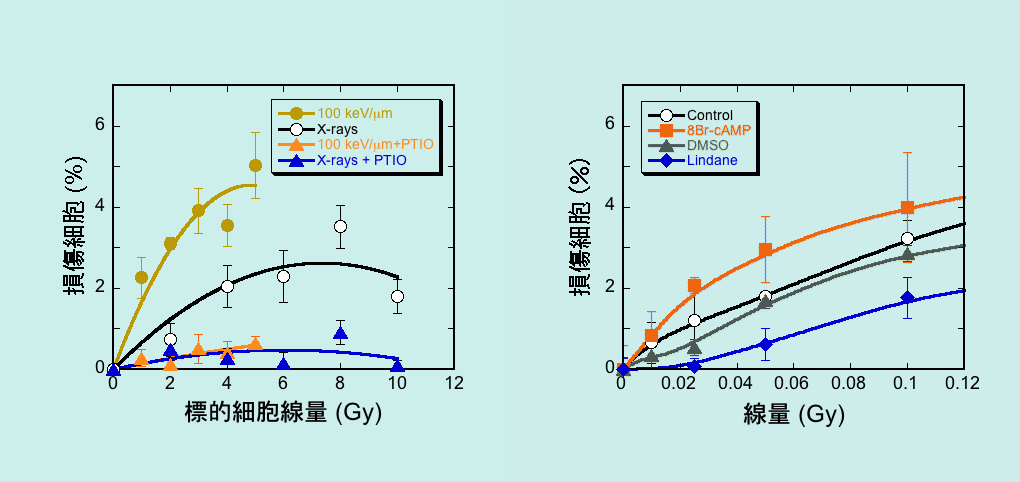放射線利用技術データベースのメインページへ
作成: 2006/02/07 古澤 佳也
データ番号 :020252
照射のバイスタンダー効果
目的 :隣接非照射細胞に及ぶ放射線効果伝達の調査
放射線の種別 :粒子線
放射線源 :サイクロトロン、シンクロトロン
線量(率) :1〜数粒子/細胞
利用施設名 :日本原子力研究開発機構(TIARA)、放射線医学総合研究所(HIMAC)
照射条件 :大気中
応用分野 :基礎研究、放射線防護
概要 :
放射線誘発バイスタンダー効果は非標的細胞における放射線の影響である。この効果は被照射細胞からの放射線ストレス物質が非照射細胞に伝達される経路が考えられ、非照射細胞に損傷を誘発するほか、細胞の分化や増殖の亢進など多岐にわたる。実験によっては、ミクロン級の精度で細胞を照射するマイクロビーム照射装置を必要とする。
詳細説明 :
放射線誘発バイスタンダー効果の論文は1992年にNagasawa & Little(Cancer Res 52; 6394-6396)によって、非標的細胞における間接的な放射線の影響として発表された。この効果は細胞間隙ギャップ接合を介すか培地中へ分泌される物質を介し、被照射細胞からの放射線ストレス物質が非照射細胞に伝達される経路が考えられている。
バイスタンダー効果によって非照射細胞にDNA損傷や染色体異常が誘発されるほか、細胞の分化や増殖の亢進など多岐にわたった応答が観察されている。実験によってはミクロン級の精度で細胞を照射するマイクロビーム照射装置を必要とすることから研究可能な施設が限られている。
バイスタンダー効果の発現モデル
バイスタンダー効果の信号伝達経路は細胞間ギャップ結合を経由したものと細胞外分泌物質によるものに大別でき、さらにリガンドや受容体を経由した信号の伝達経路が存在する(図1)。
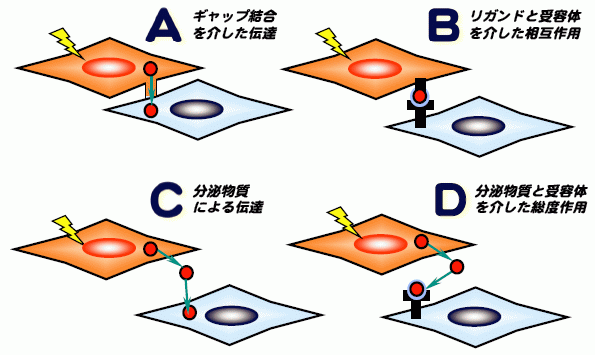
図1 放射線誘発バイスタンダー効果の発現モデル(原著論文1より引用・改変) ギャップ結合を介したバイスタンダー因子の伝達と細胞外分泌物質による効果の伝達が考えられる。これにリガンドと受容体が加わる場合もある。
細胞間ギャップ結合を経由した信号伝達効果は、細胞間接着装置のひとつであるギャップ結合の中のチャンネルを使った細胞質中のイオン・アミノ酸・ヌクレオチドなど主に低分子物質の交換経路を介して起こっていると考えられる。これは被照射細胞内で発生した放射線応答による化学産物(バイスタンダー因子)が、隣接していて放射線をあびていない非照射細胞にギャップ結合を介して移行し、非照射細胞内で様々な二次的変化が誘発されることに起因するバイスタンダー効果であると考えられている。これにはギャップ結合のチャンネルを開く(8Br-cAMP)あるいは閉じる(Lindane)作用を持つ薬品を培地に添加することでバイスタンダー効果の増強や抑制を観察(原論文3)することが出来る(図2右)。
細胞外分泌物質による信号伝達では、被照射細胞から分泌される物質すべてがバイスタンダー因子となり得る。この物質の中には拡散性の高い低分子物質から分泌性の高い生体高分子物質まで含まれる。この中で日本では、一酸化窒素のスカベンジャー(PTIO)等の添加によるバイスタンダー効果の抑制や、一酸化窒素量の直接測定、その発生化学物質の添加で同じ生物効果が見られることなどから、一酸化窒素誘導体がバイスタンダー因子であることが発見されている(原論文2,4)(図2左)。
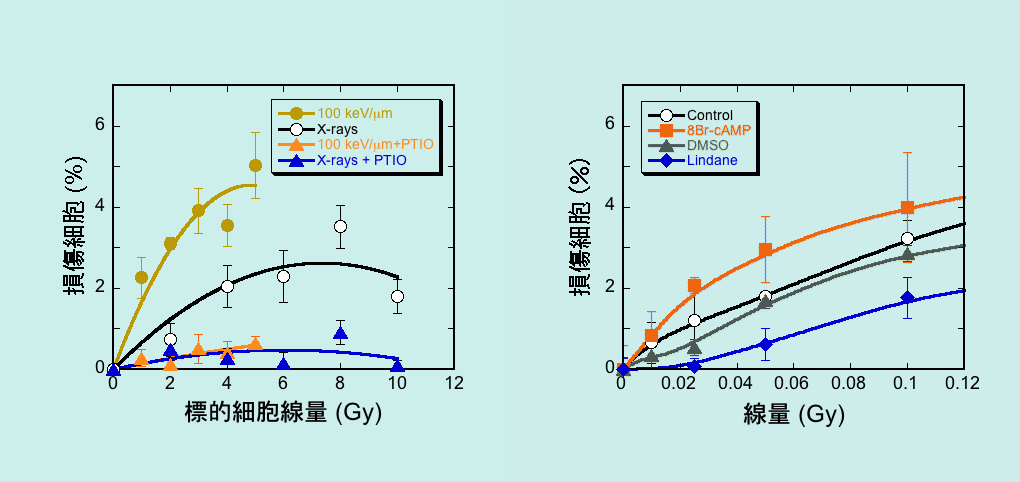
図2 ギャップ結合および細胞外分泌物質によるバイスタンダー効果とその抑制(原論文3(右図),原論文4(左図)より引用・改変) 右図:ギャップ結合を介したバイスタンダー効果による微小核形成(染色体異常生成)が、8Br-cAMP添加により増強され、Lindane添加によって抑制されている。特に低線量域(0.096Gyが各細胞核に平均1粒子照射される確立に等しい)で顕著に見られる。左図:PTIOの添加により細胞外分泌されるNO誘導体をスカベンジすることにより、100keV/μm炭素線の場合もX線の場合もバイスタンダー効果による誘発を抑制できている。
これらバイスタンダー効果は、歴史的に染色体異常等が調べられたために細胞を傷害する方向の効果が取り上げられるケースが多いが、細胞の分化や増殖を促すなど細胞にとって有利な方向に働く場合もある。また、アブスコパル効果としてがん治療で経験されている効果(がんの放射線治療で非照射部位に存在するがん組織の縮小など)にも関係していると考えられる。
マイクロビーム実験施設
バイスタンダー効果のうちギャップ結合を介したものは、隣接した細胞集団の中の特定の細胞だけを狙い打ちする必要がある。このため数ミクロンの精度で照射することが可能な放射線照射装置が必要となるが、高度な技術を要するためにこれが可能な施設は限られている。生物効果に関して論文の出ている機関は、コロンビア大学[LZ](米)、グレーがん研究所[LZ、X](英)、日本原子力研究開発機構(TIARA)[HZ]等である。最近国内の施設(原論文5,6)が充実しつつあり、放射線医学総合研究所(SPICE)[LZ]、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所(KEK・PF)[X]、若狭湾エネルギー研究センター[LZ]、京都大学・理[HZ]、長崎大学・医歯薬[X]と拡がりを見せてきていて、特に国内では異なった線質のマイクロビームの利用が可能となっている。
注)かっこ内は施設名。([ ]内のLZ、HZ、X、はそれぞれ、プロトンまたはα粒子、重粒子線、蛍光X線または単色軟X線を示す。)
コメント :
バイスタンダー効果の発見によって、直接放射線があたってない細胞であっても放射線の影響を受ける事が示された。バイスタンダー効果を考慮して議論されなければ、細胞に対する放射線の総合的効果を正しく評価することが困難になる。一方、これを正しく評価することで放射線生物効果の真の姿が浮き彫りにされるであろう。
原論文1 Data source 1:
ストレス応答研究の新展開 -放射線誘発バイスタンダー効果-
松本英樹、林幸子、金朝暉、畑下昌範、加納永一
福井医科大学放射線基礎医学教室
放射線生物研究 36, 87-99 (2001)
原論文2 Data source 2:
Induction of radioresistance by a nitric oxicide-mediated bystander effect.
Matsumoto H, Hayashi S, Hayashita M, Ohnishi K, Shioura H, Ohtsubo T, Kitai R, Ohnishi T, Kano E.
R福井医科大学放射線基礎医学教室
Radiation Research 155, 387-396 (2001)
原論文3 Data source 3:
Role of gap junctional intercellular communication in radiation-induced bystander effect on human fibroblasts.
Shao C, Furusawa Y, Aoki M, Ando K
放射線医学総合研究所
Radiation Research 160, 318-323 (2003)
原論文4 Data source 4:
Bystander effect in lymphoma cells vicinal to irradiated neoplastic epithelial cells: Notric oxide is involved.
Shao C, Aoki M, Furusawa Y
放射線医学総合研究所
Journal of Radiation Research 45, 97-103 (2004)
原論文5 Data source 5:
Microbeams of heavy charged particles.
Kobayashi Y, Funayama T, Wada S, Furusawa Y*, Aoki M*, Shao C*, Yokota Y, Sakashita T, Matsumoto Y, Kakizaki T, Hamada N
日本原子力研究開発機構、*放射線医学総合研究所
Biological Sciences in Space 18, 235-240 (2004)
原論文6 Data source 6:
バイスタンダー効果と放医研SPICE計画
濱野毅, 安田仲宏, 今関等, 湯川雅枝, 古澤佳也, 鈴木雅雄, 松本健一
放射線医学総合研究所
放射線 13, 15-23 (2005)
キーワード:バイスタンダー効果、イオンビーム、マイクロビーム、非照射細胞、放射線効果、
bystander effect, ion beam, microbeam, non-irradaiated cell, radiation effect
分類コード:
放射線利用技術データベースのメインページへ