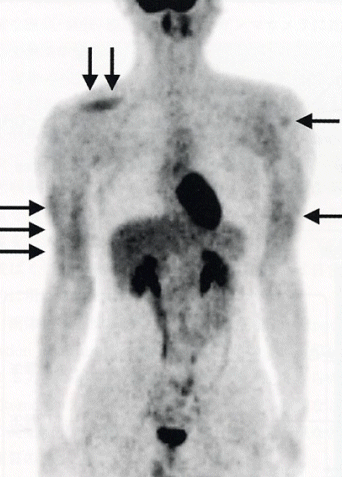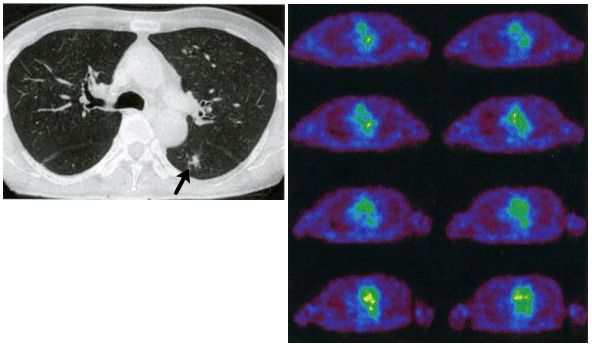放射線利用技術データベースのメインページへ
作成: 2003/12/25 山本和高
データ番号 :030257
F-18-FDG PETによるがん検診の特徴と限界
目的 :18F-FDGを用いるクリニカルPETの問題点を紹介
放射線の種別 :陽電子
応用分野 :医学、診断
概要 :
F-18標識フルオロデオキシグルコース(FDG) を用いるPET 検査が、悪性腫瘍の検出、心筋の生存能の評価、てんかんの焦点診断などに保険適用が認められ、PET検査を実施できる医療機関が急速に増加している。FDG PET検査は、様々な悪性腫瘍を、非侵襲的に、全身を1回で検索することができるのでがん検診としても利用されているが、決して万能ではない。FDG PET検査は高価であり、その特徴と限界をよく理解した上で適切に活用すべきである。
詳細説明 :
F-18フルオロデオキシグルコース(FDGと略)を用いるPET検査については、既に、このデータベースにも幾つか取り上げられている。PETを行っている医療機関のリストは、東北大学サイクロトロン・RIセンターのホームページ(http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index-j.html)に掲載されている。 FDG PET検査の内容や有用性については、それらを参考にされたい。
ここでは、がん検診におけるFDG PET検査の注意すべき点や、その限界について紹介する。
1. 血糖値の影響
高血糖では、腫瘍集積が減少し、バックグラウンドが高くなる。F-18 FDG静注前に少なくとも4時間以上の絶食が必要である。糖尿病などにより高血糖値を示す症例には、特に注意がしなければならない。水分は、尿量を確保するために、ある程度摂取した方が良い。
2.撮影タイミング
多くの悪性腫瘍では、FDGの集積ピークは1.5〜5時間後とかなり様々である。通常は静注1時間後に撮像されているが、遅いほうがバックグラウンドの正常組織の放射能が低下するので、可能なら1.5〜2時間後から撮像を行った方が良い。しかし、撮像までの時間を遅らせると、患者の待ち時間が長くなり、効率的なPET検査のスケジュールを組みにくくなる。さらに、F-18の減衰により、画像のノイズが増加するので、F-18 FDGの投与量を増やしたり、感度の高い三次元データ収集を実施したりする必要がある。
3.吸収補正
吸収補正をしないと、体表面を縁取るようなアーチファクト、肺と縦隔の境界や肝の辺縁に集積が上昇したような所見を示し、縦隔リンパ節などの評価が困難になる。吸収補正をする方が良いが、全身スキャンなど広い範囲の吸収補正のためのトランスミッションスキャンには時間がかかる。また、短時間の不十分な吸収補正はノイズを増加させ、むしろ画質を低下させる。このため、エミッションスキャンとトランスミッションスキャンの同時データ収集法も行われるようになっている。また、同じ装置でCTとPETを行うCT-PETが開発された。CTデータを吸収補正に利用することで、検査時間が短縮されるばかりではなく、形態画像と機能画像を融合できる装置で、平成15年末に医療用具として認められ、今後、急速に普及するものと予想される。
4.生理的集積
図1に、検査当日、F-18 FDG静注前にダンベルを使ってトレーニングを行った症例のFDG-PET全身像を示す。静注後は安静を確保したが上腕や右肩の筋肉へのFDG集積増加が見られる。
脳はブドウ糖をエネルギー源としており、FDGを多量に取り込むので、脳腫瘍の検索には造影MRIが適している。口蓋扁桃、唾液腺、甲状腺にも軽度のFDG集積が見られ、発声や嚥下などにより咽頭、喉頭部の小さな筋肉にFDGが集積するので、頭頚部腫瘍やリンパ節転移との鑑別には注意を要する。
心筋は、血糖値が高いとFDGを多量に取り込み、周囲の病変の診断が困難になる。
縦隔や大血管にも放射能が見られるが、これには血液プール中のFDGが影響しており、撮増時間を遅らせると減少する。また、若年者では胸腺に集積が認められることがある。乳房、特に、授乳中は強く集積する。
胃や腸管には、さまざま部位に、さまざまな程度でFDG集積がみられ、大腸がんとの鑑別が困難な場合もあり、早期胃がんの検出には適していない。肝の放射能は時間とともに低下していくが、早期の肝細胞がんの検出には超音波検査の方が効果的である。
FDG投与後2時間で、約15%が尿中へ排泄されるため、腎、尿管、膀胱が描出され、尿路系腫瘍の検出は難しい。十分に排尿させて膀胱内の放射能を減らしておかないと、アーチファクトのために膀胱近傍の直腸がん、子宮がん、卵巣がんなどを診断できないこともある。PET画像の再構成法に、従来のFBP(filtered back projection)法にかえて、アーチファクトを生じにくいOSEM(ordered subset expectation maximization)法を使用する施設も増えている。
子宮(特に生理期間中)や睾丸の描出も見られることがある。
CT-PETを用いると、FDG集積部位の解剖学的情報を同時に得ることができるので、このような生理的集積と、悪性病変の鑑別が容易になり、検査の有用性が向上する。
5.炎症性病変等
マクロファージや顆粒球などの炎症性細胞、新生血管や線維芽細胞が増殖している若い肉芽組織などもFDGをかなり多量に取り込むので、サルコイドーシス、膿瘍、肺真菌症などさまざまな炎症巣もFDG-PETで陽性に描画される。また、手術創、生検や血管造影検査の穿刺部位、放射線照射部位なども描出され、偽陽性を示すことになる。FDG投与1時間後と3時間後に2回撮影すると、炎症では2度目の集積が低下し、悪性腫瘍と鑑別できるという報告もあるが、例外も少なくない。
FDGを集積する良性腫瘍には、唾液腺のWarthin腫瘍、甲状腺腫、大腸ポリープなどがあり、それ以外に、大血管の動脈硬化性病変や、G-CSF投与後の骨髄でもFDGの集積が認められる。
6.FDG−PETで検出されない悪性腫瘍 偽陰性
悪性腫瘍を陽性像として検出するには、その腫瘍がFDGを周囲の正常組織より有意に多く取り込み、かつ、その取り込みをポジトロンカメラで集積増加部として描画できることが必要条件となる。したがって、脳や尿路系など、正常組織の放射能が高い部位は悪性腫瘍の検出には適していない。FDGの取り込みが乏しい前立腺がんや、グルコース‐6-フォスファターゼ活性を有し、取り込んだFDGを細胞外に出してしまう分化度の高い肝細胞がんの診断も困難である。
ポジトロンカメラの空間分解能はFWHMで4〜5mmであるが、臨床では画質を改善するためのフィルタリングを行うので、通常、7〜9mmとなる。空間分解能の5〜6倍以下では実際の放射能よりも低いカウントを示す部分容積効果が問題となり、小さな腫瘤は検出困難となる。粘膜にそって薄くひろがる食道がんの検出率は、粘膜層に留まるpT1a期では0%、粘膜下層までのpT1b期でも20%と報告されている。また、間質性成分や嚢胞性成分が多く、単位体積あたりの悪性細胞数が少ない場合も偽陰性が増加する。
図2は、細気管支肺胞上皮がんの症例で、CTで左肺下葉に小さな腫瘤像が認められる(矢印)が、FDG-PETでは、異常集積を指摘できない。肺がんのFDG-PETは、感度96%、特異度73%、正診率90%と良好であるが、内部に空気を含み、すりガラス様陰影(ground-glass opacity)を示す肺胞上皮がんや高分化型腺がんは偽陰性となることが多い。
山中湖クリニックでの16,287回の検診で177例にがんを発見したが、FDG-PETで検出できなかったのが83例と、ほぼ半分近くあったと報告している。
FDG-PETは、悪性腫瘍のスクリーニングに有用な方法であるが、決してすべての悪性腫瘍が検出できるわけではない。FDG-PETの特徴を十分に理解して、適切に利用していくことが重要である。
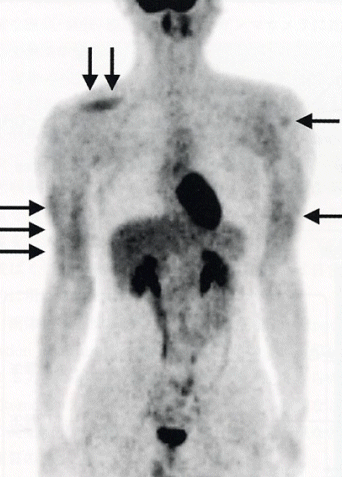
図1 FDG投与前にダンベルでトレーニングをした症例のFDG-PET像。上腕、右肩の筋肉へのFDG集積が増加している(矢印)。心筋、縦隔、肝、腎、尿管、膀胱などへの生理的集積も認められる。(原論文1より引用)
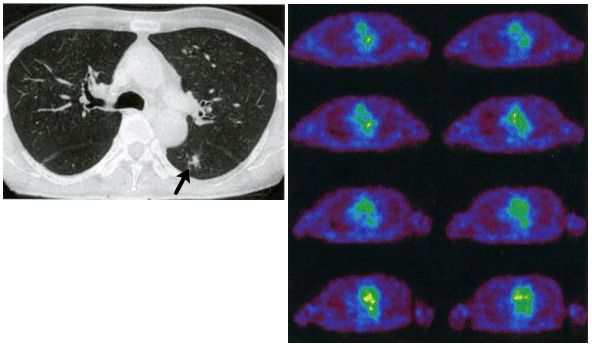
図2 細気管支肺胞上皮がんの胸部CT像(左)と、同症例のFDG PET胸部横断像(右)CTで左肺下葉に腫瘍性病変(矢印)が認められるが、FDGの明らかな集積は認められない。(原論文2より引用)
コメント :
FDG-PETは高価な検査であるが、近年、急速に普及している。がん検診の方法としても広く利用されるようになってきたが、FDG-PETも万能ではない。FDG-PETの特徴と限界を十分に理解して、必要に応じて他の検査法を併用する必要がある。また、FDGにかわる、優れた新しい腫瘍イメージング製剤の開発と、その臨床応用も不可欠と考えられる。
原論文1 Data source 1:
Clinical PET これだけは知っておきたいFDG-PETの知識
坂本 攝、中本裕士、千田道雄
臨床画像 2003;19(4):448-461
原論文2 Data source 2:
クリニカルPET−FDGの臨床応用− 肺癌
織内 昇
画像診断 2003;19(10):1142-1150
参考資料1 Reference 1:
FDG-PETの原理と評価法
窪田和雄
画像診断 2003;20(10):1118-1128
キーワード:クリニカルPET、フルオロデオキシグルコース、がん検診、腫瘍診断、clinical PET,fluorodeoxglucose;FDG,cancer screening,tumor diagnosis
分類コード:
放射線利用技術データベースのメインページへ